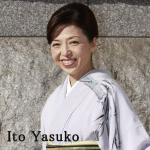○本場奄美大島紬とは
本場奄美大島紬とは奄美大島で製造されている伝統的工芸品の「本場大島紬」ことです。
伝統的工芸品ですので鹿児島で製造されてるものと製法上異なる点はございません。
製法は同じですが製造している反物の雰囲気は奄美産が黒っぽいもの(泥染め)が多いのに対し 鹿児島産は明るい色(白、多色)が多いようです。
泥染めは奄美でしか出来ないので鹿児島で製造する場合、奄美に糸を送る必要があります。
○泥染め、藍染めのこと
泥染めは奄美では「純泥染め」と「草木泥染め」の2種類に分類されており前者はテーチ木(車輪梅) の煮汁で染めて泥で媒染し真っ黒に染めたもの指し、 後者はその他の草木で染め泥で媒染したものを指します。
藍染めは奄美でも昔から行われてきましたが現在では本藍で染める所は少なくなり、 化学藍を用いて染めてるところが多いです。
○マルキとは(9マルキ、7マルキの希少性)
マルキとは大島紬のタテ糸における絣糸の量を示す製造用語で1マルキが80本と考えます。
なのでそれぞれ下記の本数の絣糸が入っていることになります。
9マルキなら9.6×80=768本
7マルキなら7.2×80=620本
しかしこれには、下記の条件であることが必要となります。
9マルキなら「絣糸2本・地糸1本」の割合で入っている場合・・・1
7マルキなら「絣糸2本・地糸2本」の割合で入っている場合・・・2
現在流通しているものは下記のものがほとんどです。
9マルキ「絣糸1本・地糸2本」・・・3
7マルキなら「絣糸1本・地糸3本」・・・4
なのでそれぞれ別の呼び方があり
1・「本9マルキ」または「9マルキ一元」
2・「本7マルキ」または「7マルキ一元」
3・「9マルキ」
4・「7マルキ」または「7マルキカタス」
9マルキも7マルキもタテ糸の総本数は同じですので絣糸が多いという事は
柄を構成する糸が多いという事で柄が細かく繊細になります。
稀少性においては「1」「2」「3」「4」の順番です。
マルキ以外にも「柄の大きさ」や「刷り込む色」、「総絣の有無」、などにより
製造の難度は大きく異なりそれにより稀少性の順番も変動したりします。
繊細な柄というか複雑な柄を作るときには刷り込みという技法で様々な色の絣点を作ることがあります。
薔薇の大島紬(http://www.kimono-bito.com/item.php?item_id=010298)は
柄を構成している部分以外の所(背景)に全て色を入れることで
一見大胆な柄を繊細に表現しています。

また、この大島紬(http://www.kimono-bito.com/item.php?item_id=010299)は
一元カタス越式というタテ糸の配列は「絣2本・地糸3本」です。

現在このような配列で製作される事はほとんどありません。
この配列は通常の絣点の間隔と微妙に異なるので揺らぎを感じやすくなっています。
○奄美布の名古屋帯
奄美の帯の特徴は、奄美大島紬の生地質の特徴と共に、
「色合いの明るさ=今の時代に合っている」ことだと思います。
泥大島紬は濁った色合いなので、これまで、濁った帯にしか合わせることが
できませんでした。その雰囲気は、一昔前の時代感覚になりがちです。
それに対して、この奄美布の帯は、色合いがとても今風のパンチが
効いたきれいな明るい色合いであることで
ぐっと洗練された若々しさが生まれています。
少し明るい、少し綺麗ではなく、ぐっと明るく美しいので年齢を問わず素敵に合います。
シックな濁ったきものを生き生きと見せてくれるのは、色のハーモニーとも言えます。

また、奄美の帯の場合、ほどほどにしっかりした生地の厚みですが
お太鼓に芯を入れないと柔らかいです。
前には、芯を入れない方が涼しいので
前に芯をいれなければ、生地質(すっきりして軽い)から
夏を含めた1年中使っていただけます。
本来の八寸名古屋帯は、お太鼓に芯を入れませんし
九寸名古屋帯は、前にも芯を入れますが
奄美帯は、前に芯を入れない方が年中使えるという
新しいタイプの帯となっています。